塾なしで地域のトップ高校を目指しています。
このブログは、
事情があって塾には通えないけれど
行きたい高校に行くために
家庭でどうやって勉強すればいいの?
という小・中学生とその保護者の方へ
我が家ではこんな風にやっていま~す!!
をシェアするために開設しました。
中学生の勉強ルーティン、検定試験への挑戦
模試、定期テスト、通知表など
子どもの許可を得られたものを公開しています。
時々、小学生の子の勉強についても書いています。
家庭学習を始めるまでは何をしていたか?

未就学時代は、砂場と絵本。
現在中学生の子どもが
家庭学習を始めたのは小5の終わり。
ほぼ6年生からのスタートです。
家庭学習を始めるまでに何をしていたか?
未就学の間は近所の公園の砂場で遊んでいました。
理由は、知育と言うよりは
マンション住まいなので
幼児の足音などで苦情が来たらどうしよう。
なんてビビりな性格なので、晴れてる日、
子どもが起きている時間はなるべく外で過ごしました。
本もたくさんは買えないので
図書館もよく利用していて
週1で40冊かりて本を入れ替えて
常にいろんなジャンルの本が手に取れる環境
にしていました。
小学生時代、宿題以外にやっていたこと
それまでに学校の宿題以外で
やっていたお勉強といえば
幼児期しまじろうから続けてきた
ベネッセの進研ゼミの
(チャレンジタッチではなく)紙のドリルです。
学校の教科書に準拠していましたので
小学校のカラーテストはほぼ満点でした。
家庭学習を始めてから小6の1年は
家で用意したドリルと進研ゼミを続けました。
⇩中学生になる前の家庭学習はこんな感じ⇩
家庭学習のきっかけと、大切にしていること

ある日突然子どもに『勉強したい』と言われる
現在中1の子どもが小5の終わりに
『高校はトップ校に行くから❗』
当時はお友達の影響だと思いますが、
元々、嫌いではなかった勉強を
自らやると言い出したので、
家庭学習のやり方を調べることから
今の生活が始まりました。
勉強よりも生活リズムが優先!!
家庭学習を始めたけれど、
それまでの生活リズムは変えたくなかったので
(幼児がいるので就寝時間を遅くしたくなかった)
中学生の就寝時間に幼児が合わせるのではなく
幼児の就寝時間に中学生が合わせます。
⇩【20時消灯】中学生の就寝時間と睡眠時間⇩
勉強には、賢くなるにはまず、
栄養と体力が大事だと思っているので
我が家では教育費はよりも食費にお金をかけます。
⇩学力向上の秘密はね・・・⇩
志望大学は将来就きたい職業から逆算で決めた!

行きたい会社が見つかった!!
行きたい憧れの高校が決まり
家庭学習が習慣化してくると今度は
『行きたい会社ができた❗』と言うのです。
大学よりも先に職業を決めていました。
その会社に入社するには
この大学のこの学科で学びたい
それには高校は地域のトップ校を目指す
将来なりたい職業から逆算して
【大学→高校→中学の内申点をしっかり取る!】
と決め毎日勉強をする動機になっています。
⇩塾なしでもオール5は可能です⇩
塾講師に【その高校は塾なしは無理!!】と言われる。
ちなみに、地元最王手の塾模試にお邪魔した時に
志望校を聞かれ、公立トップ校だと伝えると
その高校は塾なしでは入れません!!
と、ハッキリ言われてしまいました。
プロの塾講師さんが仰るんだから
普通はそうなんでしょう・・・だけど
この世に絶対と言い切れることなんてないですよね?
挑戦するくらいは許していただきたいものです。
⇩今のところは公立トップ校A判定です⇩
塾なしは金銭的な理由と本人の希望

きょうだい全員分の塾代の捻出が難しい
塾なしを選んだ一番の理由はやはり金銭面。
高卒夫婦のサラリーマン家庭で子ども3人分の
大学費用を用意するのが目標ですが
塾代まではちょっと…
家庭学習を習慣化することで
勉強を毎日することは
毎日歯磨きをするように当たり前である
と認識するのが理想です。
人に教わるより、自分でわかりたい!!
もう1つの理由はウチの子どもが、
人に教わるよりは
自分でじっくり参考書を読んで
自分で出来るようになりたい気持ちがあるようです。
人に教えるのは好きだけど、教わるのは嫌い・・・
同じ理由で
無料の季節講習もお断りしています。
⇩費用は0円!!友達に教える勉強法⇩
これから具体的な我が家の勉強の進め方や
勉強計画、失敗談や使用教材について記事を書きます。
我が家の取り組み、失敗などが
どなたかのヒントになることがあれば幸いです。
コメント欄は各記事の1番下に用意していますので
お気軽にお使いいただけたらと思います。
検索して中学生もたどり着くかもしれません
コメントを見た方が捉え方によっては気分を害されるかな?
と、迷うコメントは承認できないことがあります。
ご了承ください。
お読み下さりありがとうございました。
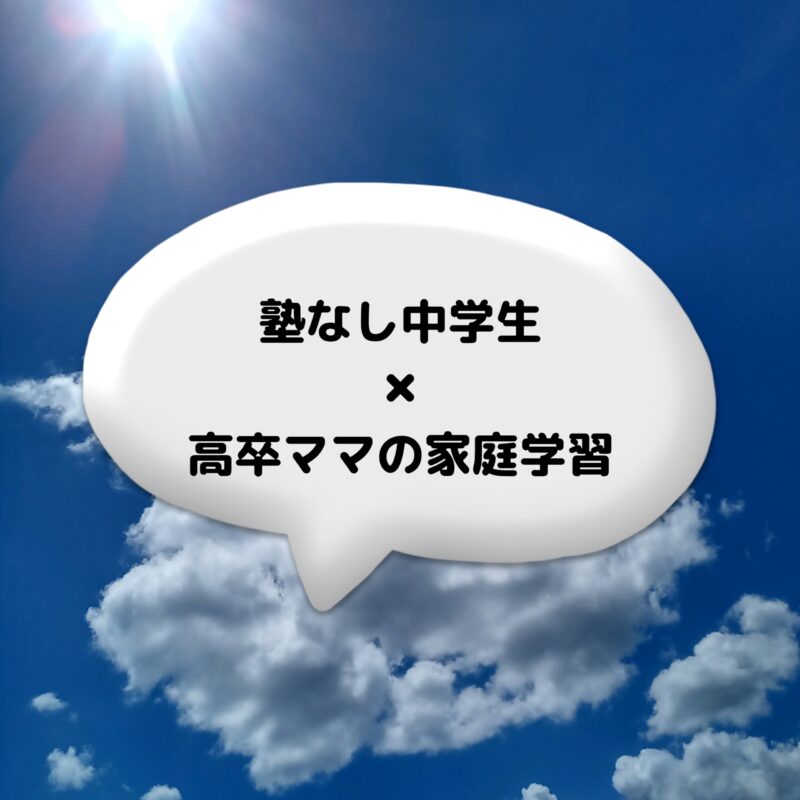

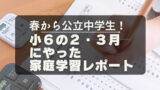




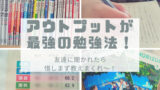
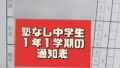
コメント